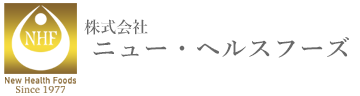腸内環境
タグ:"腸内環境" の一覧ページです。
毎回健康に関する情報を提供しております
今回は善玉菌が免疫力をUPするという話です

腸内環境と免疫力の関係について
全身の免疫力を低下させないためには腸内環境を整えることが大切です。
このことがクローズアップされること自体、現代人の免疫力が昔に比べて低下している証拠なのかもしれません。
昔の人の多くは、バイ菌を含む微生物や寄生虫と共生していました。
しかし、生活環境が整うと同時に「清潔志向」も高まり、体内に程よく共生していたバイ菌や寄生虫まで排除されました。
こうしたバイ菌の排除が免疫異常によるアレルギー疾患を生んだのではないかという専門家もいます。
つまり、昔の人はバイ菌や寄生虫と共生することで免疫力が養われていたのかもしれません。
清潔になった日本新の腸内環境
清潔になった日本人の腸内環境は昔よりも良くなったというとそうでもありません。
その逆です!
現代は高脂肪の摂取量が増えました。
そのため、悪玉菌は増える一方です。
悪玉菌が増えると全身的に様々な悪影響を及ぼします。
その1つが「病気にかかりやすくなる」などの免疫力の低下や免疫機能の異常です。
なぜ悪玉菌が増えると免疫力低下になるの
なぜ、悪玉菌が増えると免疫力が正常に動かなくなるのでしょうか?
なぜ、善玉菌は免疫力を強化すると考えられるのでしょうか?
以下の文で説明していきます。
大腸粘膜にも免疫細胞が点在している
これからの文章に出てくるワードに「免疫系」とあります。
「免疫系」とは、外敵から自分の体を守るシステムのことで、もともと人間に備わっている機能です。
ヘルパーT細胞には2種類ある
免疫系の最高司令官のヘルパーT細胞(Th)には2種類あります。
Th1:ウイルスやガンに侵された細胞などの免疫を担当する細胞
Th2:タンパク質などの小さなものの免疫を担当する細胞
Th1とTh2はどちらか一方が活性化すると、もう一方が抑制される仕組みになっています。
そして大腸粘膜にもこのヘルパーT細胞(免疫細胞)は点在しています。
つまり、腸にも免疫系が働いているのです。
それもそのはず、腸というところは、私たちが口に入れたものすべてを引き受けるところです。
ですので、基本的には何がやってくるかわからない、あらゆる意味で体内で一番汚染されやすい場所ともいえます。
未消化のたんぱく質と免疫細胞の関係
乳酸菌などの善玉菌はおもに炭水化物を分解して腸内をイキイキさせますが、ウェルシュ菌などの悪玉菌は、おもにタンパク質を分解して体に有害なガスをつくります。
肉食に偏りがちな現代人
肉食に偏りがちな現代人は、タンパク質の摂取量が増えたため、中には十分に分解・吸収されずに大腸に送られるタンパク質もあります。
こういうタンパク質を「異種タンパク質」といいます。
悪玉菌がタンパク質を分解するときにつくり出すガスは、大腸粘膜に対して毒性を持っているため、粘膜を傷つけます。
すると異質タンパク質は、粘膜に侵入しようとするので、それを防ぐために大腸粘膜に点在するTh2が活性化されます。
過剰になるとアレルギー反応をおこす
しかし大腸粘膜のTh2の活性が過剰になると、やがて全身の粘膜に広がり、タンパク質が粘膜に触れるとアレルギー反応を起こすようになります。
たとえば・・・
花粉症では、花粉というタンパク質が目や鼻の粘膜に触れて、かゆみなどのアレルギー症状を起こします。
同時にTh2の活性が上がるとTh1の活性は下がるので、ウイルスに侵された細胞やガン細胞を上手く処理できなくなり、風邪やインフルエンザなどの感染症やガンにかかりやすくなります。
乳酸菌の細胞壁が免疫力を強化
Th1とTh2のバランスを回復するのに、乳酸菌が役立ちます。
乳酸菌の細胞壁に含まれるリポ多糖体という物質はTh1活性を上げる働きががあります。
そのため、ウイルスに対して強い免疫力を回復し、ガンにもなりにくくなります。
また、Th1活性が上がるとTh2活性は下がるのでアレルギー疾患にもかかりにくくなります。
まとめ
アレルギーが酷くて鼻水が止まらない人は乳酸菌をとる習慣をつけるといいかもしれません。
これからの生活の参考にしてください。
※今回の記事は後藤利夫先生監修「腸イキイキ健康法」を参考にしました。
きのこは植物ではなく、菌類の仲間になります。
きのこが注目されるのは「菌活」と言われる通り、腸内環境を整える働きや免疫力を高める働きが腸の働きが活発化し、身体全体の調子を整えてくれます。
精神面も安定させてくれます。
レンジ塩きのこ

材料/作りやすい分量(出来上がり700g)
まいたけ・しめじ類・・各大1パック(計700g)
生しいたけ・・4枚(130g)
えのき茸・・大1パック(200g)
塩(きのこの重量の1%)・・小1強
C&C+・・1袋
作り方
① まいたけ、しめじ、えのきは石づきを除き、えのきは長さを4等分に切る。すべてほぐす。しいたけは石づきを除いて軸は裂き、笠は7mm厚さに切る。
② 耐熱皿に①を入れて塩をふって混ぜ、まんべんなく馴染ませる。ラップをふんわりとかけて電子レンジ(600w)で8分加熱し、粗熱が取れるまでそのまま蒸らす。
③ 冷めたらC&C+を混ぜ冷蔵庫で保存(3〜4日可能保存)
色んな料理にアレンジする。
塩きのこチーズトースト

材料/2人分
レンジ塩きのこ・・140g
食パン(6枚切り)・・2枚
ピザ用ソース・・大2
ピザ用チーズ・・40g
コンドラーゲンV・・少量
作り方
① ピザ用ソースにコンドラーゲンを少量混ぜておく。
② 食パンにピザ用ソースを等分にぬり、レンジ塩きのことチーズを等分にのせる。
③オーブントースターでこんがり焼く。
塩きのこと豆腐のかきたまスープ

材料/2人分
レンジ塩きのこ・・150g
木綿豆腐・・小1丁(200g)
だし・・2カップ
しょうゆ・・大1/2
卵・・2個
小ネギ(小口切り)・・少量
コンドラーゲンV・・1袋
クッキングミネカル・・小1/2
作り方
① 豆腐は5cm角に切る。
② なべに出汁を温め、レンジ塩きのこと①を加えて煮立て、クッキングミネカルとコンドラーゲンVを加えて煮立て、しょうゆで味を整える。
③ 卵を溶きほぐしてまわし入れ、フワッとなったら火を消す。
器に盛り小ネギを散らす。
栄養と料理参照

私たちの腸内には、およそ100兆もの細菌がすみついているといわれています。
その種類は約300種類、重さにすると約1kgにもなります。
腸内細菌はただ単に消化、吸収、排泄に関わるだけでなく、体に必要なビタミンを作ったり
外敵の侵入を防いだりして、私たちを守っています。
腸内細菌は、群生する野草のように仲間同士でまとまって腸内にすみついています。
その群れを「腸内フローラ(花畑)」と呼んでいます。
この腸内フローラはその性質や機能によって大きく「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の
3つのグループに分けられます。
**健康を保つ善玉菌**
善玉菌は私たちの健康を保つ有益な働きをするので、有用菌とも呼ばれています。
その代表選手が乳酸菌です。
ビフィズス菌や植物由来の枯草菌(こそうきん)も乳酸菌の仲間です。
これらは、栄養素の消化や吸収をサポートしています。
ですから、善玉菌が少なかったり働きが悪いと、栄養が十分に吸収されず、そのまま
便として出てしまいます。
また、善玉菌はビタミンB群やビタミンK等のビタミン類、女性ホルモンや
副腎脂質ホルモン等のホルモンを生産しています。
さらに乳酸や酢酸などを生成し、腸内の酸性度を一定に保つ働きもあります。
この酸は、腸内の腐敗を抑えて下痢や便秘を防いだり、
ウイルスや毒素の侵入を阻止します。
腸のぜん動運動を活発にする効果もあるので、排便もスムーズになります。
酸のおかげで、私たちはキレイな腸を保てるというわけです。
そのうえ、善玉菌には体の免疫システムを活発にして免疫力を高める働きもあります。
このように有用な善玉菌ですが、加齢とともに減っていきますので、
良い生活習慣を身につけてしっかり育てていきましょう。
**有毒物質をつくる悪玉菌**
善玉菌とは逆に、からだに害を及ぼすのが悪玉菌です。
悪玉菌が増殖すると腸内で腐敗醗酵が起こりやすくなり、アンモニアや硫化水素などの
有害物質が発生します。
このため、お腹が張ったり臭いオナラが出たりします。
また、発ガン性物質の産生量も増えます。
これらの有害物質は腸から吸収されて、肝臓に運ばれて解毒されるので、
肝臓の負担が大きくなります。
あまりにも量が多くて肝臓で処理しきれなくなると、毒素は全身に運ばれてしまいます。
その結果、細胞がダメージを受け、頭痛や肌荒れ、倦怠感等の様々な不快な症状が出てきます。
動脈硬化やガンなど、生活習慣病を引き起こす原因にもなります。
**優勢な方に加勢する日和見菌**
善玉でも悪玉でもない中立な立場の菌で、代表的なものに大腸菌があります。
日和見菌は、善玉菌が優勢な時には善玉菌に加勢し、悪玉菌が優位の時には悪玉菌に加勢します。
この日和見菌が、腸内細菌の大半を占めています。
ですから、良い腸内環境を保ち、日和見菌が悪玉菌に加勢するのを防ぐことが大切です。
これらの3種類の細菌は腸内で常に縄張り争いをしています。
善玉菌が優勢なら私たちの体は元気です。
ところが、偏った食生活やストレス、加齢、抗生物質の服用などで、腸内環境は
すぐに悪化します。
つまり、腸内が汚れて免疫力が低下し、生活習慣病にもかかりやすくなります。
健康な人の腸には、乳酸菌が多く存在し、病気の人の腸は善玉菌が少なく、
腸内環境が乱れています。
私たちの健康を左右しているのは腸内細菌であると言っても過言ではありません。
今の食生活やライフスタイルが腸内環境に大きな影響を与えます。
善玉菌が喜ぶライフスタイルを実践して腸を整えましょう。
※今回の記事は「断食しないで断食効果」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。

乳酸菌とは、腸内で糖を分解して乳酸を作り出す細菌の総称です。
代表的なものに、ビフィズス菌や枯草菌、ヤクルト菌、ブルガリア菌等があります。
乳酸菌は、悪玉菌の増殖を抑えて、腸内の環境を整えて、腸の働きを活性化します。
病原菌が腸に侵入するのを防ぎ、有害物質が腸壁に吸収されるのを妨げ、
素早く体外に排出します。
免疫力を高めたり、ビタミンをつくる働きもあり、私たちが健康に過ごせるのは、
乳酸菌のお陰であると言っても過言ではありません。
人間の体にはもともと乳酸菌が棲みついており、離乳期までの赤ちゃんの腸では
ビフィズス菌の割合は90%以上になっています。
ところが、年齢とともに悪玉菌の割合が増えるので、腸内環境が乱れて、さまざまな病気が
引き起こされると考えられています。
ですから乳酸菌を増やすことが大切です。
最近では「生きて腸まで届く」をうたい文句にした、サプリメントやヨーグルトをよく見かけるようになりました。
実は、口から摂取した乳酸菌のほとんどは、胃酸や胆汁酸にやられて腸にたどり着く前に
死んでしまうのです。
生きて腸まで到達するのはほんの一握りです。
乳酸菌は腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を退治して、腸の若返りや血液の浄化に大きな力を発揮します。
しかし、口から摂取した乳酸菌はもともと腸内に棲んでいた乳酸菌とは違うため、いずれ排泄されます。
ですから、常に補給する必要があります。
味噌や、ぬか漬け、キムチなどの発酵食品や、乳酸菌のエサになるオリゴ糖を積極的に摂るとともに
サプリメントを利用しましょう。
オリゴ糖は、大豆やタマネギ、アスパラガス、ネギ、にんにくなどに多く含まれます。
なお、死んだ乳酸菌も役に立たないわけではありません。
食物繊維のように有害物質を吸着して体外に排出する働きがあります。
死んでいても生きていても、乳酸菌には腸をキレイにする効果があるというわけです。
※今回の記事は「断食しないで断食効果」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。

毎日の食生活習慣を振り返って「日々の食事」「お通じはどうだったか」をしっかり結び付けて、ご自身の腸内環境を結びつけるクセをつけましょう。
そじて、食に対するきちんとして知識を身につけましょう。
例えば、ヨーグルトを食べれば健康になれると思っている人も多いと思います。
便秘気味の人でヨーグルトを食べることを習慣にしている人も多いでしょう。
でもそれだけでは便秘は解消しません。
肉食を習慣にしている人は、肉を食べた後の自分の腸内環境がどうなるのかを知ることも大事です。
動物性脂肪をとりすぎると、腸内環境は悪玉菌が優位となり、バランスが崩れてしまい様々な病気を引き起こしてしまいます。
**食物繊維が腸内環境の悪化を防ぐ**
ヨーグルトの効用を高め、肉食による腸内環境の悪化を改善させる為には食物繊維をとることが大事になります。
この食物繊維をとるにはどうしたらよいかを、ご自身の食習慣も含めて考えていきましょう。
**おからは食物繊維がたっぷり**
食物繊維が豊富な食品として、ぜひ活用してほしいのが「おから」です。
おからは、豆腐の製造過程で、豆乳を絞った時にでる、いわば残りカスです。
しかし、おからにはタンパク質、カルシウム、カリウム、大豆イソフラボンなどの体に良い栄養素がたっぷり入っています。
そして、おから50gあたりに食物繊維が約5gも含まれています。
これは、豆腐よりもはるかに多く、同じ分量のゴボウと比較しても約2倍の量です。
おからのメニューを1品増やすだけでかなりの分量の食物繊維を補えます。
**まとめ 腸を強くする食習慣のポイント**
・腸を整えるプロバイオティクスで善玉菌を優位にする
プロバイオティクスとは、生きたまま腸に届き、人体に良い影響を与える微生物やそれらを含む食品のことです。
代表的なのが、ヨーグルト、キムチ、納豆などの発酵食品です。
これらを多くとるほど腸内の善玉菌を優位にすることができ、悪玉菌を抑制します。
・腸にためない食物繊維でいつもスッキリ
食物繊維は消化酵素でも分解されず大腸にそのまま届いて、腸内の老廃物や有害物質などをからめとって排出する腸のお掃除屋さんです。
また、悪玉菌も食物繊維があると増殖できず、腸内フローラのバランスも整います。
※今回の記事は辨野義己先生著書「自力で腸を強くする30の法則」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。

腸を強くするのに一番大切なこと
それは、大腸をスッキリとキレイに保つことです。
大腸は食べかすが排泄されるまえに、最後にたどり着く場所です。
その大腸に食べかすが滞って汚れていたら、生ごみと同じように腐敗して
有害物質を発生させ、これが病気の原因となるわけです。
すなわち、大腸に食べかすが運ばれてきたら、スムーズに排泄させることが
健康を保つために大事になります。
ここで大切なのが、3つの力です。
1つはお通じをスムーズにするためのもととなる材料を「つくる力」。
そして「育てる力」。最後に「出す力」です。
良いお通じのためには、腸に良い食べ物をしっかり摂取する必要があります。
しかも、ただつくるだけでなく、腸内環境のバランスをなるべく崩さず、
良い材料となるものを食べなければなりません。
そこで、腸にとって最良の食べかすとなるのが、食物繊維です。
かつて食物繊維は消化できないため、人間の体に必要ないものと思われていました。
でも、現在では腸内をキレイに保つために重要な役割を果たすことが証明されています。
そして今度は食べかすを排泄しやすいように食物繊維を育てなければなりません。
それには腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑えるような食事をし、
腸内フローラのバランスを整えることが重要です。
腸内環境を良くするためには、ヨーグルトや発酵食品を積極的にとり、
生きたまま腸に届く善玉菌を送り込みましょう。
食べるだけでなく「出す」というところまでが腸の仕事のサイクルです。
その為に、食事だけでなく運動にうよって下半身の筋肉を鍛えて、
日頃から出す力を強化しましょう。
つくる力=食物繊維
育てる力=ビフィズス菌・乳酸菌
出す力=腸腰筋(お尻周辺の筋肉)
これらの力を高めれば、腸内環境はいつも良好に保たれて腸が強くなるだけでなく、
肥満防止、免疫力向上、さまざまな病気の予防にもつながります。
今からでも腸を強くする知識を身につけて健康な未来を手に入れましょう。
※今回の記事は辨野義己先生著書「自力で腸を強くする30の法則」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。

体を守る免疫、ウイルスやガン細胞を攻撃する免疫細胞は腸から作られています。
小腸・大腸合わせて体の70%の免疫細胞が集中しています。
特に小腸の表面にある絨毛(じゅうもう)には
病原菌などの外敵から体を守るリンパ節に指令を出すセンサーが
突起1つにつき30~40個も存在します。
そのため、小腸は「免疫の司令塔」とも呼ばれています。
また、大腸には体の20%にあたる免疫細胞が集中しています。
さらに、小腸の免疫機能を正常に働かせるために、大腸にすむ善玉菌の
働きが不可欠であることが最近の研究でわかってきました。
病気を未然に防ぐ力も、腸内フローラのバランスが大きく左右するということになります。
**セロトニンも腸でつくられる**
セロトニンはやる気を引き出し、精神を安定させるための脳内物質です。
セロトニンが不足すると、うつ病の原因になります。
セロトニンをつくるためにはトリプトファンという物質が必要です。
食べ物からトリプトファンを合成するために必要なのが腸内細菌です。
腸内細菌のバランスが悪いと、トリプトファンの合成に必要な
酵素やビタミンB6を腸内で産生できません。
体だけでなく心の健康のためにも腸内細菌のバランスが大切になってきます。
腸が喜ぶ食事をたくさんとって、腸をいたわりましょう。
乳酸菌や食物繊維をたくさん摂ることで腸内環境も良くなりますので
たくさん食べましょう。
※今回の記事は辨野義己先生著書「自力で腸を強くする30の法則」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。

腸内の細菌のバランスは善玉菌が優位になると体調も良いです。
腸内の善玉菌が優位になると
★免疫力アップ
★整腸作用
★消化、吸収の促進
上記のような効果があり、結果的に
♬老化防止
♬健康促進
♬アレルギー改善
♬美肌
♬気力充実
などのうれしい結果がおこります。
そのため、外見は若々しく、体調は万全、やる気に満ちた行動的な性格
まさに無敵な状態の人生が送れそうです。
逆に悪玉菌が優位になると
×腸内腐敗
×細菌毒素の産生
×発がん性物質の産生
等の現象が起こり
結果的に
↓病気になりやすい
↓老化促進
↓アトピー、花粉症
↓肌荒れ
↓無気力、疲労
などの症状が出ます。
**乱れた生活が悪玉菌を増やす**
腸内フローラのバランスが整っていると病気知らずの生活が送れます。
多くの人が理想とする「ピンピンコロリ」の天寿を全うすることができるでしょう。
ただ、気を抜いた生活を送ると腸内フローラのバランスは知らないうちに崩れていきます。
例えば、肉食過多、油のとりすぎ、野菜不足、運動不足などです。
すると悪玉菌が増えてきます。
最初に起こるのが、下痢や便秘。
これは腸内フローラからの「悪玉菌が増えて危険だよ」のサインです。
その時点で腸内環境を良くするように生活を改めましょう。
若さの秘訣は腸内フローラにあります!
腸を元気にしていきましょう。
※今回の記事は辨野義己先生著書「自力で腸を強くする30の法則」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。

厚生労働省はこれまで、日本人の食事について、
エネルギーと食塩の摂りすぎ、カルシウム不足などを伝えていましたが、
最近では「食物繊維」と「カリウム」も摂取不足であると指摘しています。
「食物繊維」「カリウム」が不足すると、高血圧や糖尿病、心筋梗塞といった
生活習慣病の要因となりますので、毎日の食生活で不足しないように
心がけましょう。
**食物繊維は肥満、糖尿病、心筋梗塞を防ぐ**
食物繊維は人間の消化酵素では消化されない成分です。
水に溶ける「水溶性食物繊維」と水に溶けない「不溶性食物繊維」があります。
前者は海藻類やキノコ、果物などに豊富で、後者は野菜やいも類、穀類、豆類に
多く含まれています。
五大栄養素ではありませんが、生活習慣病に役立つ様々な働きが注目されています。
**食物繊維の主な働き**
糖の吸収を穏やかにして、食後の血糖値の急上昇を抑えるため、糖尿病の予防効果が期待できます。
さらに、便のカサを増やすことで排便を促します。
また、食物繊維の豊富な食品は、硬いものが多く、自然と噛む回数が増えます。
そのため、食べすぎを防ぎ肥満を予防します。
その他、小腸でコレステロールの吸収を抑える働きがあり、血中脂質のバランスを整えて
動脈硬化を防ぎます。
大腸まで届いて腸内細菌のエサとなり、腸内環境を整えて、便秘改善に役立ちます。
**食物繊維の摂取を増やすコツ**
まずは積極的に野菜をとることです。そして、主食を工夫してみましょう。
食物繊維は玄米や精製度の低い穀類に豊富です。
主食をこれらに替えるだけでも手軽に摂取量を増やせます。
ただ、玄米は消化されにくい傾向があるので、高齢の場合は
白米に少し混ぜたり、胚芽米にするとよいでしょう。
**カリウムの主な働き**
ミネラルの1つである「ナトリウム」と作用し合い、細胞内液の浸透圧を一定に保ちます。
ナトリウムは主に食塩の形で摂取され、とりすぎると高血圧を招きますが、
カリウムには、体内の余分なナトリウムの排出を促す働きがあります。
日本人は食塩の摂取量が多いのでカリウムをしっかりとることで、
高血圧予防に役立ちます。
**カリウムの摂取を増やすコツ**
カリウムは水溶性なので、食材の調理に工夫が必要です。
冷凍や電子レンジによる加熱などは、量・質ともに変わりませんが、
「下ゆでして、水にさらし、絞る」という調理法だと損失量が多くなります。
野菜から効率よくとるなら、生野菜サラダにしたり、塩分控えめのスープにして
溶け込んだカリウムを丸ごと食べましょう。
果物は生のまま食べられるので、カリウムの摂取源としておススメです。
ただ、糖質も多いので、食べすぎには注意しましょう。
また、穀物は、主に胚芽部分にカリウムが含まれています。
主食に玄米を使えばカリウムも食物繊維もとれて一石二鳥です。
ただし、腎臓病がある人は重症度によってカリウムを尿に排泄することが難しく、
カリウムの摂取を制限する必要があります。
※今回の記事は「日本健康マスター検定」公式テキストを参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。