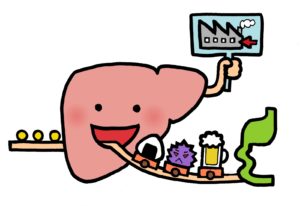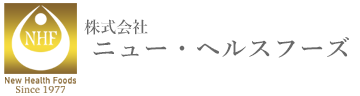今回はコレステロールについてのお話しです
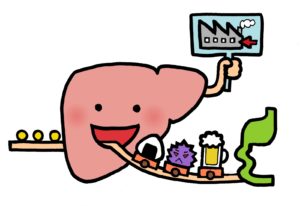
体内でも合成されるコレステロール
コレステロールは、さまざまな食品に含まれていますが、体内に取り込まれるのはそのうち40~60%です。
一方、コレステロールは肝臓でも日々合成され、血液に混ざって体中に供給され、細胞膜や胆汁酸、ホルモンの材料になっています。
肝臓で合成される量は食事で摂取する量の3~7倍にもなります。
つまり、食事で摂取したものと、肝臓でつくったもの、両方のコレステロールがあります。
健康診断のコレステロール値は、これらがどれくらい血液中にあるかを示したものです。
コレステロール値を気にする人は、コレステロールを多く含む食品を控えようとします。
しかし、肝臓には、体何に供給されるコレステロールを一定量に調整する働きがあります。
食品から多く摂取すると合成する量を減らし、摂取量が減ると多く合成するため、食事でコレステロールを控えてもその分すぐコレステロール値が下がるというわけではありません。
もちろん食べすぎはNGですが、厳密に例えば「卵は1日1個まで!」とか決める必要はないようです。
コレステロールの役割
コレステロールの役割には主に次のようなものがあります。
✔関連細胞膜の構成成分になる
✔性ホルモン、副腎皮質ホルモンなどの材料になる
✔胆汁酸、ビタミンDの材料になる
気を付けること
エネルギーや飽和脂肪酸を摂りすぎると、肝臓でコレステロールの合成が増加するといわれています。
コレステロール値が気になる方は気をつけましょう!
※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
ビタミンDの主な働きには次のようなものがあります

1.カルシウムとリンの吸収を促進
ビタミンDは食物として体内に入った後、肝臓と腎臓で活性型ビタミンDになります。
活性型ビタミンDは小腸でカルシウムとリンの吸収に必要なたんぱく質の合成を助け、腸管からカルシウムの吸収を高めます。
2.カルシウムの骨への沈着を助ける
血液中のカルシウムを骨に運搬し、カルシウムが骨に沈着するのを助けます。
また、筋力を強くする働きもあることがわかっています。
3.血中カルシウム濃度を調整
血液中にはカルシウムが一定濃度で存在します。
濃度が下がるとビタミンDが活性化され、腸管からのカルシウムの吸収を促進しカルシウムの濃度を維持します。
カルシウムは筋肉の収縮に関わるため、ビタミンDが血中のカルシウムの濃度を調整することで、筋肉などの活動も正常に保たれます。
どのような食品に入っているのか
ビタミンDはおもに魚介やキノコ類に多く含まれます。
ビタミンDはアンコウの肝、サケ、イワシ加工品を筆頭に色々な種類の魚介に含まれきくらげを代表としたキノコ類にも豊富です。
穀類や野菜類には含まれておらず、肉類にもほとんど含まれていません。
.
効率の良い食べ方は
油脂と一緒にとることで吸収率が高まります。
ビタミンDは脂溶性のため、それ自体に脂質を含んでいる動物性食品からとると吸収率が上がります。
キノコ類などの植物性食品は、炒め物や揚げ物など、油を使う調理法で食べると吸収率が上がります。
また、キノコ類には紫外線にあたるとビタミンⅮにかわる成分が含まれています。
キノコ類は日光に当てて成分を増やすしてから食べると良いです。
※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる」を参考にしました。