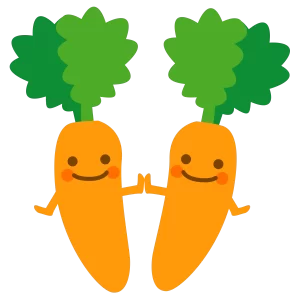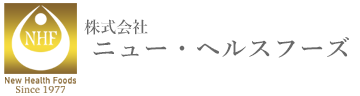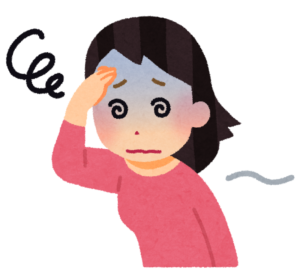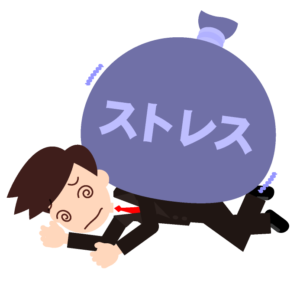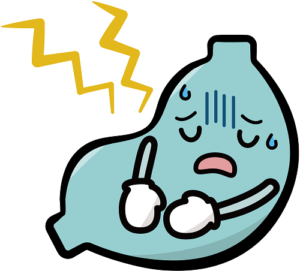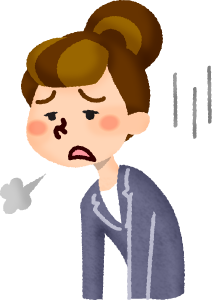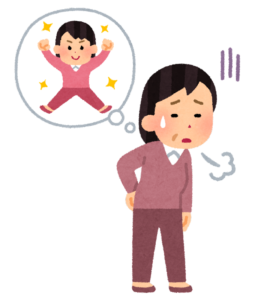カテゴリー:日記の一覧ページです。
今回は人参についてのお話しです
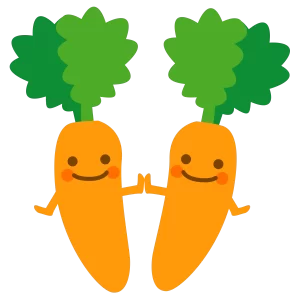
βカロチンが豊富な食材
人参の濃いオレンジ色はβカロチンが豊富に含まれている証拠です。
西洋種のオレンジ色は、豊富なβカロチンによるものです。
食物繊維もたっぷり含まれていています。
なかでも水溶性食物繊維のペクチンが多く含まれています。
カルシウムやカリウムなどのミネラルも豊富です。
また、赤みのある東洋種にはリコピンが豊富に含まれています。
βカロチンには抗酸化作用があり老化を予防するとされているほか、体内でビタミンAに変換され、免疫力を強化するとされています。
ペクチンは血糖値の急激な上昇を抑え、コレステロールの吸収を抑制することで、糖尿病や動脈硬化の予防に働くことが期待されます。
人参の皮の部分にはβカロチンが豊富です。
人参の皮はとても薄く、出荷地で洗浄されるときにとれています。
ですので、そのまま調理するか、たわしで表面をこする程度にしましょう。
※今回の記事は飯田薫子先生寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
今回は花粉症の対策についてのお話しです

症状
花粉症は、花粉が原因のアレルギー性疾患で、鼻炎や結膜炎などがあげられます。
侵入してきた花粉を追い出そうと身体の免疫機能が過剰に反応して、くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、涙目といった症状があらわれます。
重症の人では微熱やだるさ、皮膚のかゆみといった症状があらわれることがあります。
対策
花粉症の治療は、薬を使って症状を抑えるのが主流です。
症状が軽い時期に治療を行いましょう。
ケアとして最も大切なことは花粉を「つけない」「取り除く」ことです。
外出時にはマスク、帽子、ゴーグル等でガードして、体をはらってから花粉を落として家に入りましょう。
同時に、体の免疫機能を正常に保つことが大切です。
腸内環境も関係する
腸には体の免疫細胞の約60%が集まっているといわれています。
その環境が悪化すると免疫機能に異常が生じるため、発酵食品や食物繊維をとって腸内環境を整えましょう。
また、ビタミンB6は免疫機能を正常に保つい働きがあるので十分に摂取しましょう。
過剰な活性酸素に注意
過剰な活性酸素はアレルギー症状を悪化させるので、ビタミンA,C,Eなどの抗酸化ビタミンを積極的にとりましょう。
おススメ食品
人参・・・βカロチンが豊富で、抗酸化作用を発揮する
バナナ・・・免疫機能を正常に保つビタミンB6を多く含む
ヨーグルト・・・腸内環境を整える乳酸菌が豊富
ピーマン・・・抗酸化作用のあるビタミンC、βカロチンが豊富
モロヘイヤ・・・抗酸化作用のあるビタミンC、E、βカロチンが豊富
しそ・・・抗酸化作用のあるβカロチンが豊富
※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
今回はニキビの原因とおススメ食材についてのお話しです

ニキビは、毛穴に詰まった皮脂が原因
ニキビは、毛穴に詰まった皮脂が原因です。
その皮脂を原因としてアクネ菌などのニキビの原因菌が増殖して、炎症がおきて悪化します。
皮脂分泌の多い思春期だけでなく、大人にもできるのは古い角質のせいです。
お肌では28日周期で皮膚の新陳代謝が行われます。
しかし、ストレスや不規則な生活などで代謝が悪くなると角質が厚くなって、毛穴をふさいでしまいます。
それがニキビの原因になってしまいます。
対策
肌の代謝がスムーズに行われるように、栄養バランスの良い食事と、睡眠をしっかりとることが大事です。
洗顔で肌を清潔にしておくことも大切です。
そのうえで、積極的に摂取したい栄養が、肌の再生を促すビタミンB2や、肌の健康に役立つビタミンB6です。
また、便秘になって腸に腐敗便が溜まったままでいると、老廃物が体内に取り込まれ、ニキビを悪化させます。
食物繊維や発酵食品を十分とり、便秘を予防していきましょう。
おススメ食材
玄米・・・ビタミンB6,食物繊維が豊富
卵・・・ビタミンB2が豊富
バナナ・・・善玉菌の餌になるオリゴ糖が豊富
ヨーグルト・・・腸内環境を整える
※今回の記事は飯田薫子先生・寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。
今回は貧血の対策についてのお話しです
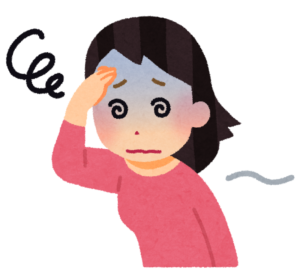
貧血とは
貧血とは、血液中の赤血球に含まれる赤い色素(ヘモグロビン)の濃度が低下した状態です。
ヘモグロビンには全身に酸素を運ぶ働きがあるため、貧血になると身体が酸欠の状態になります。
疲労感や息切れ、頭痛などの症状があらわれます。
赤血球の生成に必要なビタミンB12や葉酸が不足しても貧血になります。
貧血の対策
貧血の対策には食生活の見直しが大切です。
無理なダイエットをしたり、朝食を抜いたりすると食事からとれる鉄の量が不足します。
特に女性は、月経や妊娠などで多くの鉄を必要とします。
規則正しい食生活で十分な鉄分を補給しましょう。
食品中の鉄
食品中の鉄には肉や魚などの動物性食品に含まれる「ヘム鉄」と、野菜などの植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」に分けられます。
その吸収率を比較すると、ヘム鉄は15~25%、非ヘム鉄は2~5%です。
吸収が良いのはヘム鉄ですが、食事全体の栄養バランスも考えながら食べていきましょう。
鉄の吸収率を良くするためにはビタミンCを同時に摂ると効果的です。
反対に緑茶や紅茶、コーヒーに含まれる苦味成分タンニンは、鉄の吸収を阻害します。
鉄のことを考えると食事と一緒に飲むのはやめた方がいいかと思います。
また、食品添加物として使われるリン酸塩鉄の吸収を悪くするといわれています。
ハムやソーセージなどの加工食品の食べすぎには注意しましょう。
※今回の記事は飯田薫子先生寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
今回は冷え性と血行不良についてのお話しです

血行が悪くなると冷え性に発展
血行が悪くなるのは血液循環を助ける筋力の低下や、ストレス、不規則な生活、温暖差などによって血流をコントロールする自律神経が乱れることが原因です。
栄養不足も冷えの原因になります。
エネルギー不足で体内で十分に熱が作れなくなるからです。
血行不良、冷え性の対策
「冷えは万病のもと」と言われるように血行不良による冷え性は肩こりや関節痛、めまい、アレルギー、不眠など様々な不調を招きます。
生活の中で血流を改善する対策をとりましょう。
食事で大切なのが、筋肉とエネルギーの材料になるタンパク質と、その代謝に関わるビタミンB6を十分に摂取することです。
そして食事と運動で筋力をアップして冷えの改善に努めましょう。
血行を促進する働きのあるビタミンEが豊富な食べ物や、生姜やニンニクなどをとるのも効果的です。
その他食事以外では就寝前の入浴もおススメです。
おおすすめの食材
・鶏むね肉:必須アミノ酸をバランスよく含んでいる
・赤ピーマン:ビタミンB6を多く含む
・ニンニク:血液の流れを良くするアリシンを含む
・ナッツ類:血管を広げて血液の流れを良くするビタミンEが豊富
・ショウガ:辛みの成分ショウガオールが体を温め、血行促進が期待される
・玄米:ビタミンB6のほか、糖質を分解するビタミンB1も多く含む
・イワシ:血液の流れを良くするEPAが豊富
※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
今回は食欲不振についてのお話しです

食欲不振
食欲不振はほとんどの人が経験あると思います。
食欲不振を引き起こす原因は様々ですが、主にストレスや疲労、不規則な生活などが原因でおこります。
食欲不振は、食欲や内臓の働きをコントロールする自律神経が乱れる為、空腹を感じなくなったり、胃腸の働きが悪くなったりするのです。
炭水化物に偏った食事やビタミンB1不足によってエネルギーが十分に作れなくなると、体の機能が低下して食欲不振になることもあります。
また、食欲不振が原因で、胃腸の病気やうつ病のような精神疾患が原因のこともあります。
その場合はまず、病院で治療をすることが先決です。
食欲不振の対策
体力の維持、回復のために少量でも良いですので規則正しい生活を心がけましょう。
特にビタミンB1が不足すると十分にエネルギーが体内で作られず、食欲も低下するので積極的に摂取をしましょう。
食意欲が出ないと、簡単に食べられるおにぎりや、うどんなどの炭水化物で済ませようとしてしまいます。
そうなると栄養が炭水化物に偏りがちになります。
そのため、タンパク質の補給も意識して行いましょう。
香味野菜や酸味のある食べ物も食欲を増進させてくれます。
おすすめ食材
・カツオ:エネルギー代謝を助けるビタミンB1が豊富
・にら:にらに含まれるアリシンが食欲を増進してくれる
・セロリ:独特な香りが食欲を増進してくれる
・鶏ササミ:消化が良く胃に優しい
・酢:料理に使うとサッパリした味わいになる
※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
今回はストレスについてのお話しです
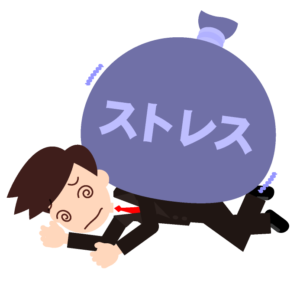
ストレスについて(いらいら・落ち込み)
ストレスとは日常の生活でおこる変化が刺激となって生じる心や体の反応をいいます。
症状として、イライラや気分の落ち込み食欲の落ち込み、増加、疲労感などがあげられます。
原因は睡眠不足などいろいろありますが、一番多いのは家庭や職場での悩みや不安、怒りなどの心理的要因です。
このようなストレスの状態が続くと、心身が疲弊して心の病気にかかってしまうこともあります。
ストレスの対策
ストレスに気付いたらまず、心と体を休ませてください。
睡眠を十分にとって自分がリラックスして気分転換しましょう。
エネルギー不足になると心も体も元気が出ず、ストレスに対する抵抗力が低下するので、栄養バランスを考えた食事をすることも大事です。
抗ストレスホルモンの生成に不可欠なビタミンCや、セロトニンの原料となるトリプトファン(アミノ酸の一種)なども十分に補給しましょう。
おススメ食材
レバー・・・セロトニンなどの神経伝達物質の生成に使う鉄を補給
納豆・・・ トリプトファンを豊富に含む
牛乳・・・トリプトファンが豊富
玄米・・・糖質の分解にかかわるビタミンB1を含む
ブロッコリー・・・ストレスの抵抗力を高めるビタミンCが豊富
※今回の記事は飯田薫子先生寺本あい著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
今回は胃もたれについてのお話しです
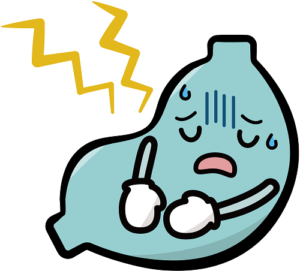
胃もたれ
胃もたれとは、消化機能が低下して、食べ物が胃に長く留まっている状態です。
胃もたれは一般的に食べすぎや飲みすぎ、油っこい食事など、胃腸に負担のかかる食生活や、ストレスによる自律神経の乱れが原因で起こります。
胃のぜん動運動が低下して消化不良になり、食べ物が長く胃に留まってしまいます。
例えば多量のアルコールは胃を強く刺激して胃の粘膜を傷つけ、胃の動きを悪くするため、胃もたれを起こします。
また、アルコールは利尿作用があるため、脱水症状になり、吐き気や頭痛をおこします。
対策
一時的な胃もたれの場合、先ずはお腹がすくまで胃を休めることが大切です。
ただし水分補給は大切です。
食事をするときは脂の多い肉や、食物繊維が多く硬い野菜を避け、消化の良い食事を心がけます。
とはいえ、タンパク質は胃粘膜の材料となるため不可欠です。
胃粘膜を保護する働きがある、ぬめり成分のあるオクラや長芋、胃粘膜の修復作用が期待されるビタミンUが豊富なキャベツやブロッコリーなどと一緒にタンパク質を摂るといいでしょう。
胃の消化吸収が低下しているため、消化を助ける食べ物も効果的です。
例えば、大根には、デンプンを分解するアミラーゼや、脂肪を分化するリパーゼなどの消化酵素が入っていて、食べ物の消化を促進する働きがあります。
おススメの食材
長芋:ぬめり成分が多く含む
キャベツ:ビタミンU(別名、キャベジン)が多く含まれる
グリーンアスパラガス:ビタミンU,タンパク質が豊富
豆腐:脂質が少なく、消化吸収しやすい
バナナ:不足するカリウムが豊富
大根:熱に弱いのですりおろして食べるのが良い
シジミ:アルコールを分解して肝臓を助けるといわれるオルニチンを含む
※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
今回は疲労やだるさの原因についてのお話しです
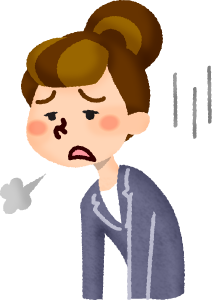
疲労の原因
働きすぎや睡眠不足、ストレスなどで、人は肉体的な疲労や精神的な疲労を感じます。
その原因の一つとしてあげられるのが活性酸素です。
活性酸素とは体内に取り込まれた酸素の一部が変化したもので、他の物質を酸化させる力が強い酸素のこと。
細菌やウイルスを攻撃する働きなど、免疫機能で重要な役割を持っています。
しかし、老化や過労などで体の機能が低下して、体内に過上に活性酸素が増えると、正常な細胞も攻撃してしまい、疲労や老化の原因になります。
対策
疲労は思考力や体力を低下させるだけでなく、免疫力も弱めます。
疲労が蓄積する前に対策をとる必要があります。
疲労の回復の基本は、十分な睡眠と栄養バランスの良い食事です。
ビタミンB1、B2、パントテン酸などをしっかりとりましょう。
さらに積極的にとりたいのが、活性酸素から身を守る働きのある抗酸化作用のある栄養素です。
代表的な栄養素としてはビタミンCや鶏むね肉などに含まれるイミダゾールジペプチドです。
おススメの食材
・そば:ビタミンB1.B2が多い
・豚肉:ビタミンB1を多く含む
・レバー:たっぷりのビタミンB群でエネルギーチャージの効果が期待できる
・レモン:クエン酸やビタミンCの補給によい
・赤ピーマン:緑ピーマンよりもビタミンCが多く、抗酸化作用がある
・鶏むね肉:アミノ酸が豊富
今回は汚れた腸と活性酸素についてのおはなしです
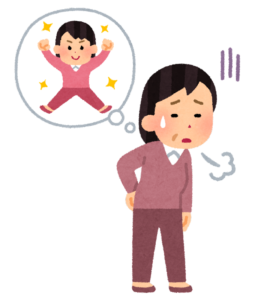
腸内環境と便秘
歳をとるにつれて善玉菌は減ります。
腸内環境も崩れてきます。
若い時には張りがあった腸がゆるみ、腸粘膜も薄く頼りない感じになります。
肌が衰えてたるんでくるのと同じです。
ぜん動運動も不活発になるので、便秘に悩む人が増えてきます。
このような腸の老化が進行するにつれて、肌がくすみ、シミ、シワも目立つようになります。
歳をとるとある程度は仕方ありません。
ところが、若いのに常に悪玉菌が多く、腸年齢が実年齢よりも高い人が増えています。
腸は非常にデリケートな臓器ですから、ライフスタイルに何か問題があるとダイレクトに反応します。
大量の活性酸素
腸年齢が高いということは腸の汚れが酷いわけですから、健康面でも美容面でも様々なトラブルが出てきます。
悪玉菌が増殖して腸が汚れていると、有毒ガスや発がん性物質が発生しやすくなります。
お腹に溜まるガスの量は、多い人では2~3リットルにもなります。
これを抑えるために、今度は大量の活性酸素が発生します。
活性酸素は酸素の仲間で、生命を維持するために不可欠のものです。
ウィルスが体内に侵入した時、白血球は活性酸素を利用して病原体を殺します。
腸も有害物質の毒素を取り除くため、活性酸素を出動させます。
このように活性酸素は有効な防御システムではあるのですが、増えすぎたりすると、逆に細胞を傷つけてしまいます。
細胞の老化
活性酸素の強力な酸化作用は、細胞を老化させ細胞膜を破壊します。
酸化とは簡単に言えばサビることです。
活性酸素が過剰に発生すると全身がサビてしまうわけです。
活性酸素にさらされて腸の細胞の遺伝子が傷つくと、細胞が変異を起こしてガンに発展すると考えられています。
また、腸内で発生した有毒ガスが吸収されて全身に運ばれると、からだの至る所で活性酸素が大量に発生します。
腸が汚れていると日常的にこれが起こるので、全身の細胞に与えるダメージははかり知れません。
血液も汚れ血管壁もサビてしまいます。
これまで、動脈硬化の原因として悪玉(LDL)コレステロールがやり玉にあげられていましたが、最近の研究ではLDLではなく、活性酸素に襲われて酸化されたLDLが動脈硬化を引き起こすことがわかってきました。
酸化されるとLDLコレステロールは過酸化脂質に変質して、血管壁にへばり付きます。
このように腸の汚れは血管の老化を招き、脳卒中や心臓病を招きます。
さらに皮膚も老化して、シミやシワが増えます。
腸年齢が高いと肌年齢まで上がってしまうのです。
老化を防ぐには、腸をキレイにして、むやみに活性酸素を発生させなことが大切です。
抗酸化酵素
私たちの体には、活性酸素を除去する機能も備わっています。
スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)やカタラーゼなどの抗酸化酵素です。
これらが自動的に活性酸素を取り除き、細胞が傷つくのを防ぐ仕組みになっています。
善玉菌はこのような酵素の活性も高めます。
また、ビタミンCやEなどの抗酸化ビタミン、ポリフェノールやカテキン、βカロテン等のファイトケミカル、天然型Nアセチルグルコサミンなどの補酵素などもサビを防ぐ力を持っています。
これらは互いに連携して、体内に発生する活性酸素を除去するために奮闘しています。
もし、このような仕組みが無かったら、活性酸素の強力な酸化作用で私たちは生活習慣病にかかりやすくなります。
私たちの体は絶えず活性酸素にさらされています。
善玉菌を増やすとともに、積極的に抗酸化ビタミンやファイトケミカルを摂取して、体をサビつかせないように心がけましょう。
腸をキレイに保つことは、生活習慣病予防、老化防止、美肌づくりに大いに役立ちます。
※今回の記事は(株)文芸社制作「断食しないで断食効果」を参考にしました。