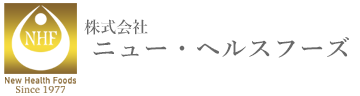血糖値の話し2020.11.13
血糖値の話し

40代後半になってきますと、段々血糖値の話しが友人との会話で出始めます。
テレビCMでも血糖値を抑える健康食品が多数あります。
血糖値の正常値は、
空腹時血糖値で100mg/dL未満、
食後血糖値で140mg/dL未満、
ヘモグロビンA1cで6.2%未満が正常値と言われています。
糖質が血糖値を上げますので、これを制限すれば血糖値は上がりません。
以下に血糖値を上げる食品をかきましたので、参考にしてください。
穀物:ご飯、ビーフン、春雨、パン、マカロニなど
麺類:蕎麦、うどん、ラーメン、きしめん、パスタなど
いも類:ジャガイモ、サツマイモ、里芋など
粉類:パン粉、片栗粉、小麦粉、餃子の皮など
野菜類:人参、かぼちゃ、蓮根、ゴボウ、そら豆、トウモロコシなど
糖質制限だけを考えたら、上記の食材を摂らないのがベストでしょうが、
人参やかぼちゃなどは、栄養が豊富に含まれていますので、
その辺りは一度お医者さんと相談してください。
また、キノコや海藻を積極的に食べると糖質制限に効果的になります。
海藻やキノコは、健康に欠かせないビタミン、ミネラルが豊富に含まれている一方で
ほとんど糖質が含まれておりません。
ヒジキは昔から「食べると髪が豊かになる」と言われている通り、海藻は髪や肌にも効果的です。
そして、キノコ類は免疫力をアップする効果があると言われています。
免疫力がアップすればあらゆる病気にかかりにくくなります。
さらに、海藻やキノコは食物繊維が豊富です。
食物繊維は便秘を防ぎ腸内細菌のバランスを整えてくれますので、積極的に摂っていきましょう。
運動は血糖値を下げてくれますので、食事制限と合わせて行うと更に効果的です。
ご飯茶碗1杯くらいなら、食後30分のウォーキングを行うことで血糖値は上がりません。
(ただし、個人差がありますので、運動後の血糖値を個人で測定してみるのも面白いかとおもいます)
ニューヘルスフーズの商品「糖減茶」は血糖値の上昇を抑えるお茶です。
静岡県の大井川で採れた山桑の葉と、瀬戸内のオリーブの葉をブレンドして作りました。
食事中など、糖が体内に入るときに摂取すると更に効果的です。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。