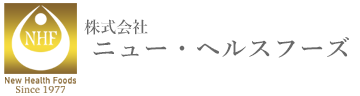今回は食欲不振についてのお話しです

食欲不振
食欲不振はほとんどの人が経験あると思います。
食欲不振を引き起こす原因は様々ですが、主にストレスや疲労、不規則な生活などが原因でおこります。
食欲不振は、食欲や内臓の働きをコントロールする自律神経が乱れる為、空腹を感じなくなったり、胃腸の働きが悪くなったりするのです。
炭水化物に偏った食事やビタミンB1不足によってエネルギーが十分に作れなくなると、体の機能が低下して食欲不振になることもあります。
また、食欲不振が原因で、胃腸の病気やうつ病のような精神疾患が原因のこともあります。
その場合はまず、病院で治療をすることが先決です。
食欲不振の対策
体力の維持、回復のために少量でも良いですので規則正しい生活を心がけましょう。
特にビタミンB1が不足すると十分にエネルギーが体内で作られず、食欲も低下するので積極的に摂取をしましょう。
食意欲が出ないと、簡単に食べられるおにぎりや、うどんなどの炭水化物で済ませようとしてしまいます。
そうなると栄養が炭水化物に偏りがちになります。
そのため、タンパク質の補給も意識して行いましょう。
香味野菜や酸味のある食べ物も食欲を増進させてくれます。
おすすめ食材
・カツオ:エネルギー代謝を助けるビタミンB1が豊富
・にら:にらに含まれるアリシンが食欲を増進してくれる
・セロリ:独特な香りが食欲を増進してくれる
・鶏ササミ:消化が良く胃に優しい
・酢:料理に使うとサッパリした味わいになる
※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。
今回はコーヒーと眠りについてのお話しです

コーヒーは14時まで
「コーヒーは眠りに悪い」というのは多くの人は常識として知っているでしょう。
では、コーヒーは何時まで飲むのがいいでしょうか。
最近の研究では「コーヒーは14時まで」。
それ以降のコーヒーの摂取は、睡眠に影響を与える可能性があると言われています。
カフェインの半減期は、4~6時間です。
飲んで5時間経ってもコーヒーの半分のカフェインが体内に残っているということになります。
カフェイン分解には意外と時間がかかります。
カフェインの代謝には個人差がある
カフェインの代謝は個人差が大きいため、実際の半減期は2~10時間と人によってかなりばらつきがあります。
また、高齢になると代謝能力は低下します。
「私はカフェインに強いから、夜にコーヒーを飲んでも大丈夫」
という人がいますが、本当でしょうか。
アメリカ・ウェイン州立大学の研究によると寝る直前にカフェインを摂取したところ、計測では1時間も睡眠時間が短縮したにもかかわらず、その違いを睡眠日記に記載した人は一人もいませんでした。
つまり、カフェインによって睡眠時間が短くなっても、それを自分で自覚するのは難しいのです。
カフェインは「寝つきを悪くする」だけでなく、睡眠の質も低下させます。
「自分はカフェインに強い」と思っている人も、夜間のカフェイン摂取は避けるべきです。
カフェインが含まれる量
また、コーヒーや紅茶以外にも、ウーロン茶やコーラなどの飲料にもカフェインは含まれます。
コーヒー1杯(150ml)のカフェイン量は「90mg」。
ウーロン茶1缶(340ml)には「約68mg」含まれます。
コーラ1缶(350ml)は「約34mg」と少ないものの、飲み放題などで何杯も飲む人がいるので要注意です。
エナジードリンクは、細い缶(185ml)だとコーヒーと同程度のカフェインの量ですが、350mlや500mlの缶だとコーヒー何杯分ものカフェイン量を含みます。
疲れている時にエナジードリンクを飲む人は多いでしょうが、家に帰ってからも眠れなくなりますし、睡眠覚醒のリズムが破壊されます。
また、血糖値を急上昇させるので、日常的に飲むと糖尿病のリスクも増えます。
カフェインの代謝は個人差が大きいです。
現在、不眠症、睡眠障害などを抱えるひと、睡眠薬を飲んでいる人、ぐっすり眠れない人は「コーヒーの門限14時」を守った方がいいでしょう。
※今回の記事は樺沢紫苑先生著書「ブレインメンタル強化大全」を参考にしました。