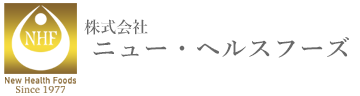カルシウムの働きと骨との関係2021.2.16
カルシウム

骨、筋肉、精神の3つ一体となって人の体は自由自在に動かすことが出来ます。
これらの3つのバランスをコントロールしているのがカルシウムです。
カルシウムの主な働きとして
・骨や歯を強くする
・筋肉の作動や脳、心臓の動きを支える
・免疫やホルモンの分泌を助ける
等が挙げられます。
もしも、血中のカルシウムが不足すると人体の生命の維持が出来なくなります。
そうならないために、「骨」にカルシウムを蓄えて
血中のカルシウムが不足した場合にすぐに引き出せるようにしています。
ですので骨の役割は、
・体全体の構造を保つ支柱としての役割
・カルシウムの貯蔵庫としての役割
上記のような役割を持っています。
ところで、このカルシウムはどのように吸収されるのでしょうか。
~カルシウムの吸収~
食品として体の中に入ったカルシウムは
小腸から体内に吸収されます。
小腸から吸収されたカルシウムは、血中に入り、骨に貯蔵されます。
このまま骨にカルシウムがどんどん集まれば骨はどんどん太くなり、硬くなります。
しかし、血中にカルシウムが不足していると、骨のカルシウムが血液中に移動します。
これを行うのが副甲状腺ホルモンです。
ですので、カルシウムを一定量供給しておかないと、せっかく骨にくっついたカルシウムが
またはがれてしまう事になってしまいます。
骨の発育が急ピッチで進む思春期以前の子供には、特にカルシウムが必要ですが、
スナック菓子、ファストフード、ジュースなどのいわゆる糖分・油分を多量に摂取すると、
カルシウムは破壊されてしまい、骨に十分なカルシウムが送られなくなります。
その結果、骨折しやすい体になってしまいます。
これは、子供だけでなく、大人にも言えることで、高齢者の骨粗しょう症の原因にもなります。
~成長にはカルシウムが必要~
成長にはカルシウムが必要不可欠です。
若いうちにカルシウムを十分な量摂取しておかないと、中高年になってから障害をおこす可能性が高くなります。
最近、問題となっているのが、ダイエットによる障害です。
ダイエットによる障害で、若い人の骨量が減少してしまっているケースが増えています。
このようなことにならない様に普段からカルシウムを多く摂取し、生活習慣を改善していきましょう。
**まとめ**
カルシウムは生きていくうえで大切な栄養素です。
日本人のカルシウムの摂取量が少ないと言われています。
カルシウムを意識した食生活を心がけましょう。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません