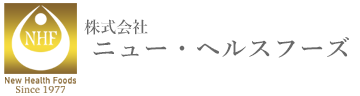ナトリウムの主な働き2021.1.6
ナトリウムについて

ナトリウムについてのお話をします。
ナトリウムの主な働きは以下の通りです。
~カリウムとともに細胞の浸透圧を維持する~
ナトリウムは細胞外液のコントロールや神経の刺激伝達に関与しています。
細胞内ではナトリウムとカリウムの比率は常に一定に保たれており
細胞内にナトリウムが増えすぎると、ナトリウムは外に汲みだされ、
細胞外のカリウムが中に取り込まれる仕組みになっています。
これをナトリウムポンプと言います。
なお、ナトリウムの過剰摂取は細胞内にナトリウムの増加をもたらします。
この時、水分も一緒に入るのでこれがむくみの原因となります。
ナトリウムが不足すると、脱水症状、消化不良、筋力低下、疲労感が起こります。
ナトリウムの1日当たりの推定必要量は600mg、食塩に換算して1.5g程度と言われています。
では、実際の食塩の摂取量はというと、成人男性で10.9g/日、女性9.2g/日。
日本人はかなり食塩を摂取していることとなります。
参考までに、塩分量は以下のようになります。
ラーメン1杯6.0g、ラーメン(汁除く)3.0g、うどん1杯5.6g、
うどん(汁除く)2.8g、かけそば1杯3.2g、カレーライス1杯2.7g
ミートソーススパゲティ1皿2.7g、寿司10貫2.6g
余談ですが、今から5000年前のヨーロッパではイワシなどの魚を漬ける際、
また、鳥などを焼いたときの味付けとして塩を使っていました。
当時、塩は貴重品として扱われました。
サラリーマンの「サラリー(salary)」の語源は、古代ローマ時代に
兵士の給与として与えられた“塩”を意味するラテン語の「サラリウム(salarium)」に由来するし、
また、salariumの“sal(サール)は英語で塩を意味する「ソルト(salt)」の語源とも言われています。
※今回の記事は糸日谷秀幸先生著書「ミネラル&サプリメントセミナー」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。