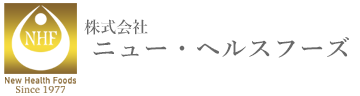アミノ酸ってどんなもの 2021.11.18

タンパク質はアミノ酸でできている
20世紀が「ビタミンの時代」と呼ばれたのに対し、21世紀は「アミノ酸の時代」と呼ばれています。
アミノ酸という名前はよく聞くものの、実際は今一つわかりにくい栄養素かもしれません。
アミノ酸とは何か
アミノ酸とは、タンパク質を構成している最小単位の物質です。
つまり、タンパク質を分解するとアミノ酸になります。
例えば肉を食べた場合、肉に含まれるタンパク質は主に胃で消化された後に分解され、小腸で吸収されます。
これがアミノ酸です。
ただし、タンパク質を構成していないアミノ酸も存在します。
例えば、脂肪燃焼にかかわる「L-カルニチン」、瞬発的なパワーを生み出す「クレアチン」、二日酔いにきくといわれる「オルニチン」。
これらはどれもアミノ酸に分類されますが、タンパク質構成していないアミノ酸です。
アミノ酸の種類
実はアミノ酸の定義にあてはまる栄養素は500種類ほどあるといわれています。
そのうちのたった20種類のアミノ酸だけが、タンパク質を構成しているアミノ酸なのです。
さらにはその中の9種類のアミノ酸だけが、タンパク質を構成しているアミノ酸で、必須アミノ酸と呼ばれています。
この9種類のアミノ酸はチームプレーが大前提となります。
どれか一つが大切なのではなく、9種類のそれぞれが反応しあって初めて力を発揮します。

一方で、アミノ酸は個々に力を発揮するケースもあります。
※今回の記事は桑原弘樹先生著書「サプリメント健康バイブル」を参考にしました。
※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。